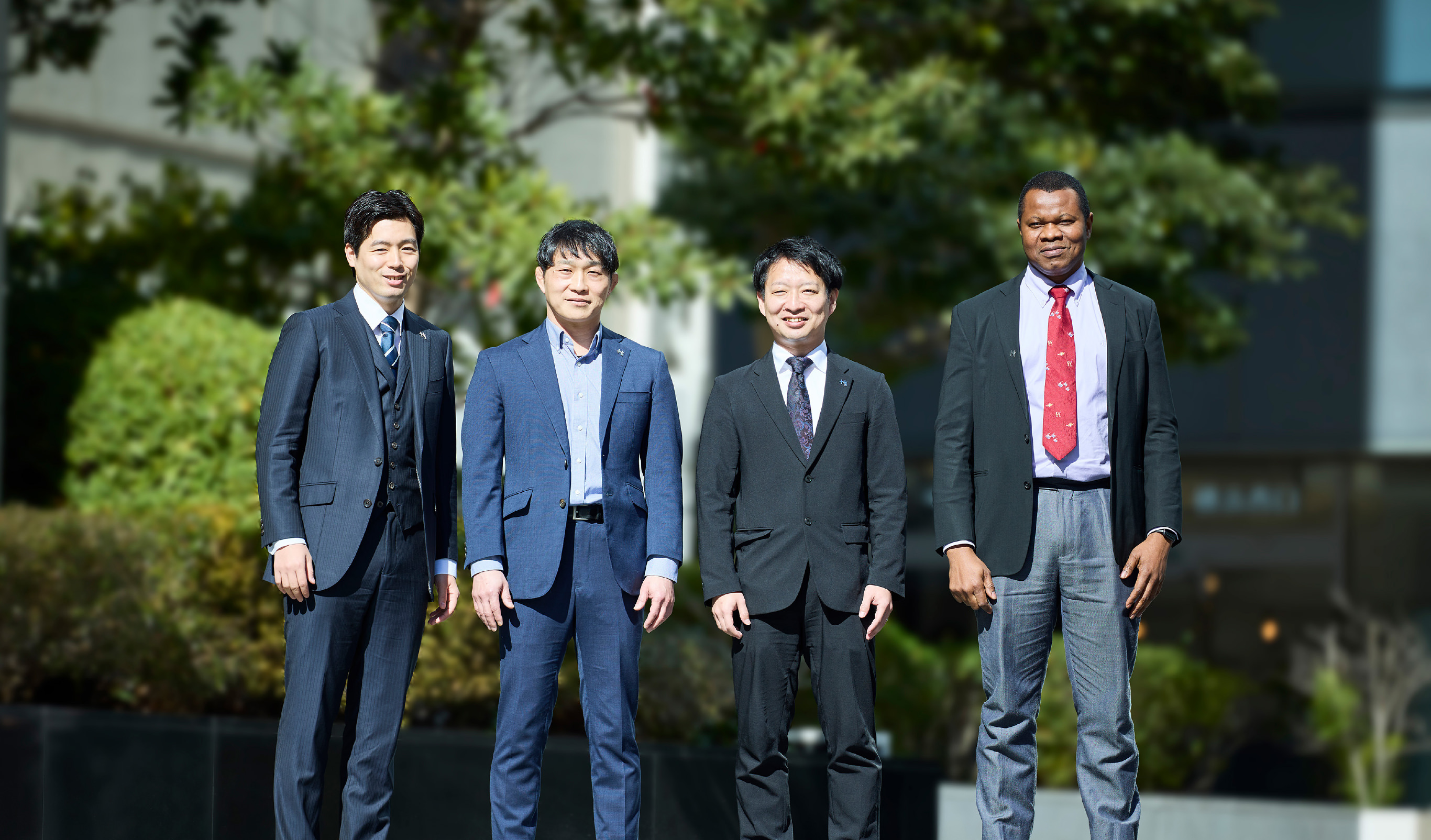世界中で地球の環境課題が取り上げられ、CO2削減が叫ばれる今、注目されているのがCO2を発生させない水素エネルギー。TBグローバルテクノロジーズ(TBG)は、この水素を利活用した水素社会を実現する選択肢の一つ、「液化水素」を輸出入するために必要不可欠となる液化水素用ローディングアームの開発・商用化に挑戦。2030年の運用開始に向けて、現在も挑戦を続けている。


H.T.
水素事業開発室 室長
2011年入社 / 経済学部・国際経済学科 卒
2011年に東京貿易マシナリー(現TBG)に入社。営業、マーケティング業務などの経験を経て、2022年、水素事業開発室・室長となる。

E.E.A.
水素事業開発室
2024年入社 / 工学部・機械工学専攻 修了
前職は原子力発電プラントの設計を担当。クリーンエネルギーである水素への興味・期待から、TBGに入社する。ナイジェリア出身。

A.T.
水素事業開発室
2023年入社 / 機械・電子システム工学専攻 修了
学生時代より社会インフラに関わりたいと考え、前職では下水処理設備に関するプロダクトを設計。TBGには未来を支える事業内容・理念に惹かれ、転職を決意。

N.N.
水素事業開発室
2024年入社 / 機械科 卒
施工管理職。前職では電力プラントの設備メンテナンスを手掛けており、ローディングアームを担当。そこでH.T.に出会い、その人柄に惚れてTBGに転職する。

2023年2月。その時、H.T.は先輩社員とともにHy touch神戸液化水素基地にいた。世界初となる液化水素用ローディングアームの荷役実証試験に立ち会っていたのだ。自国ではエネルギーの生産量が不足する日本は、液化水素を輸入に頼る必要があり、国際間の液化水素サプライチェーン構築が求められていた。海外から船で運ばれてくる液化水素を陸地にある基地に荷役する役割をローディングアームが担っている。2014年から国のイノベーションプログラムとして開発を続けてきたTBGだったが、現場にいたメンバーは感無量という表情だった。「この先輩方の想いを引き継がなければいけない。」2022年に水素事業開発室が発足する際、H.T.は室長に抜擢されて本プロジェクトの責任者となった。次に目指すのは2030年、神奈川の基地での運用開始。神戸の荷役実証試験とは異なり、実際に液化水素が社会で利用されるためには、大容量の液化水素を一度に荷役しなければならない。商用規模に足るプロダクトの開発に向けて、課題は山積みだ。そもそもTBG、ひいては東京貿易グループとしてこのプロジェクトは実現可能なのか、という根本的な問題も抱えていた。2030年の運用開始を目指すには、莫大な開発費用・リソース・期間が必要となる。この開発やプロジェクトへ挑戦するかどうかは経営判断に委ねられる。TBG、そしてホールディングスの経営陣、さらには基地局全体の施行を受注する重工業メーカーとも何度も議論を重ね、綿密に調整を続けていった。そして開発・プロジェクト続行の経営判断が降りた。「全力で支援する。任せた!」こんなに壮大なプロジェクトに臨める幸せはない。H.T.の胸中は、感謝とこれから始まる挑戦への熱量で満たされていた。

これまで、何百・何千基とローディングアームを製造してきたTBGだが、液化水素用のローディングアームの開発は困難を極めた。液化水素は−253℃と極低温であり、従来の液化天然ガス用のアームをそのまま使用することはできない。液体水素専用のローディングアームを設計する必要がある。これを担当していくのが、E.E.A.である。“解”となっているのは、液化水素を通す管に、真空二重管を使用すること。真空層を設けることで配管内部と外部の入熱・伝熱を抑制するのだ。だが、この真空二重管を用いるとアームが太く、重くなってしまうという問題があった。E.E.A.は先輩社員とともに何度も設計・施策・解析を繰り返し、構造を調整。構造解析や熱解析の経験を積み上げ、今後のプロジェクトにおいても同様の技術を迅速に活用できる体制を整えていくことになる。

H.T.が室長に任命された際、水素事業推進室は4名のみ。プロジェクトを成功に導くためには、強い仲間が必要だと感じたH.T.は、人事担当とともに採用活動に奔走した。ローディングアームの緊急離脱装置の設計を担当するA.T.も、そんなH.T.と出会って入社を決めた一人。「液化水素用ローディングアームが、きっと未来のために必要となる。」面接の際、意気投合し、現在に至る。A.T.の設計する緊急離脱装置は、液化水素の荷役中にもしも船が流されるなどした際に液化水素を配管内に封印し、船陸間のアームを安全に切り離せる“弁”のような役割を持っている。この緊急離脱装置にも改良設計が求められた。前職で全く異なるプロダクトの設計を担当していたA.T.はアームの経験が豊富なわけではない。じっくりと構造を解析し、ローディングアームへの理解を深めていく。やるべきこと、やらなくてもよいこと、意思を統一し、先輩社員とともに安全な緊急離脱装置を完成させていく。

本プロジェクトで施工管理を担当するN.N.もまた、H.T.の人柄と新たな挑戦に惹かれ、入社を決めた。前職で電力プラントのローディングアームのメンテナンスをしていた際に、H.T.と知り合った。「H.T.さんは会社を超えて、立場を超えて、気さくに話しかけてくれる人。誰からも慕われていた。」とN.N.は語る。開発チームの面々が設計したローディングアームを現場で安全に組み上げるために、N.N.は綿密な工程表をプランニングする。2030年の運用開始前にまず、2025年から2027年までの2年間をかけて、JAXAの能代ロケット実験場を借りて開発試験を行うことになるが、その工程を各方面とすり合わせていく。また、開発チームに対して施工や保守の観点を踏まえて、設計変更を依頼するのも仕事の一つ。ローディングアームは背が高く、設置ポイントが海上に面する立地ということもあり、危険と隣り合わせである。「あらゆるリスクを想定してなければいけません。水素社会の実現というロマンも第一。でもやっぱり、安全第一ですから。」とN.N.は笑う。

2022年に4名でスタートした水素事業推進室は、初号機を創り上げてきた先輩社員を含め現在18名まで増員。これまでローディングアームはTBG長岡工場内のみで製造していたが社外パートナー2社を加え、関係者は100名超となっている。この大所帯をまとめるため、H.T.はミッションステートメントを策定。「6つの遵守事項/マインド」をⅠ.安全、Ⅱ.敬意、Ⅲ.誠実、Ⅳ.成長、Ⅴ.感謝、Ⅵ.健康とした。「自分の利益のための仕事や判断は、対立や分断を生みます。自分の幸せだけを願う人が社会の未来を創ることはできません。自分以外の誰かの幸せを願う仲間たちや、ありがとうと言い合える関係から生まれる仕事が、明るい未来を創る。そう信じています。」カーボンニュートラルに向けて、液化水素のエネルギーサプライチェーンが技術的・経済的に実現可能かどうか、世界が注視する中で現在プロジェクトは進行中。もし、成功すれば各国がその後を追い、そこに市場が生まれ、液化水素を次世代のエネルギーの主役とする機運も高まるだろう。「次の世代、その次の世代の子どもたちの未来を創る。そんな仕事をしたい。」地球にやさしいエネルギー、水素社会への架け橋を仲間たちと共に描いていく。