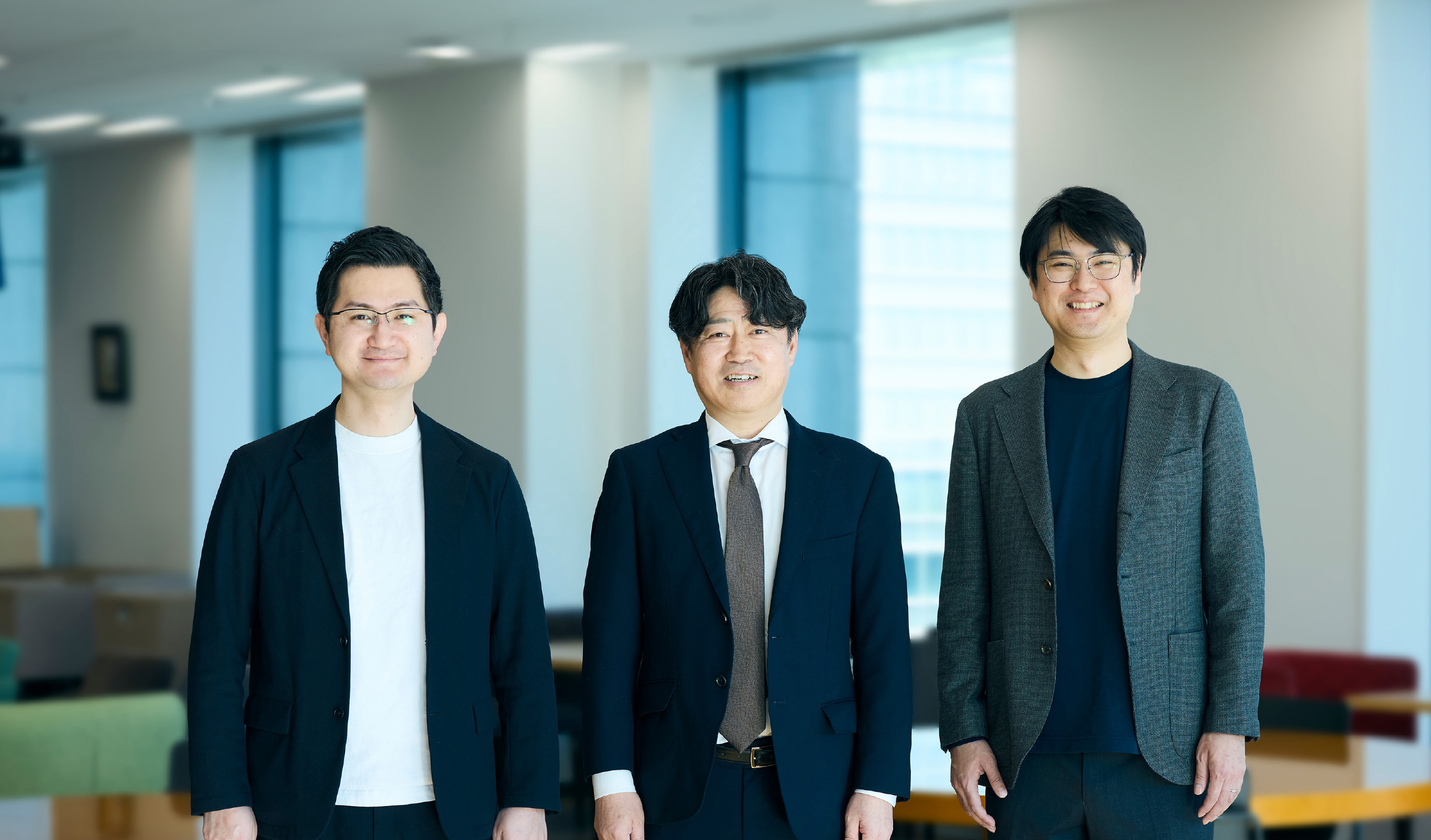設立以来、高精度を誇る各種三次元測定機の開発・製造・販売を手掛けてきた東京貿易テクノシステム(TTS)。これまで正しく“測る”ことを価値として提供し続けてきた同社が、持ち前の測定技術を起点とし、世の中のモノづくりの工程全体に変革をもたらすサイバーフィジカルシステム、略してCPS(Cyber-Physical System)の構築に社を挙げて取り組む。これは、TTSが挑む“プロセスチェンジ”の物語である。


S.K.
IoT DX領域 DXソリューションチーム チームリーダー
2022年3月入社 / 工学部 経営工学科 卒
DXソリューションチームのリーダーとしてメンバーを束ね、ソリューションの調査・企画・施策・提案を手掛ける。CPS構想においてもリーダーとしてメンバーを牽引。
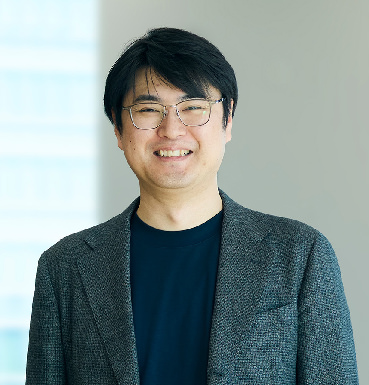
A.S.
スタイリング領域 商品開発チーム チームリーダー
2012年入社 / 情報理工学部・情報メディア工学科 卒
入社以来、設計、技術営業、商品開発とポジションを変えながらも、一貫して自動車の設計・デザインに必要不可欠なクレイモデル加工機に携わる。

N.K.
営業企画部 営業企画チーム チームリーダー
2011年入社 / 政治経済学部 経済学科 卒
国内営業、海外営業の経験を経て、現在は既存プロダクトの受注・拡販の営業企画、新プロダクトの商品企画、海外の営業拠点立ち上げ支援という3つのポジションを兼任。

TTSのメイン顧客となるのが、自動車業界。その自動車業界が「100年に一度の変革期」を迎え、デジタルシフトが加速する中、その開発・製造体制や手法は日々変化を続けている。「これまで三次元測定機のメーカーとして盤石な地位を業界内に築いてきたTTSにとって、それは危機であり、また機会でもありました。」そう語るのは、DXソリューションチームのリーダー、S.K.だ。「これまでの計測エンジニアリングの提供だけでは大きな価値とはみなされず、プラスαが求められていた。そこで、TTSが社を挙げて取り組んだのが、サイバーフィジカルシステム(CPS)構想プロジェクトです。」TTSの考えるCPS構想とは、現実世界(フィジカル空間)のデータをサイバー空間で分析・解析し、その解析結果をまた現実世界にフィードバックするといった具合に、強固にフィジカルとサイバー空間を連携させるマニュファクチャリングシステムだ。「コンピュータ上の仮想空間でプロダクトを施策・設計・性能テストするシステム、CAEでつくられたデータをベースに、実際にプロダクトを製造してみて、現実世界でテストし、またその結果を計測してサイバー空間に返してやる。この連携を密にすることで、モノづくりの世界が圧倒的に高速化、効率化され、結果、高品質で優れたプロダクトが生まれてくる。そんなプロセスチェンジを目指すプロジェクトが始まりました。」しかし、TTSには計測の技術はあるものの、CAEに関する技術は乏しかった。S.K.はパートナーを探すため、海外の著名なCAEソフトメーカー数社をピックアップ。CPS構想の概念を説き、タフな交渉を続け、そのうちの一社とアライアンスを締結した。パートナーとして共同開発をする中でも問題は続出した。何しろ、企業文化も、開発体制も、技術分野も異なるのだ。TTS社内でも様々なプロフェッショナルがプロジェクトに集うが、意見が対立することもしばしばあった。S.K.は問題が起こると常に、「CPS構想を実現した時、顧客に、世の中にどんな価値を提供できるか?」という原点に戻り、メンバーをまとめ、モチベートした。「大きなプロジェクトを一人で推進することは困難です。互いに尊敬し、同じ目標に向かって自分の役割を全うする。それがチーム運営で一番大切なことだと思います。」自分たちは世の中にない製品をつくっている。だから、困難も、失敗も当然だ。S.K.はそんな誇りを胸に抱き、旗振り役としてプロジェクトを先導した。

CPS構想に不可欠となるのは、プロダクトのデジタルデータをいかに高速、かつ高精度で、実物化できるか。精度が低ければ、結局、人の手直しが入ることになり、データと現実のプロダクトにズレが生じてしまう。また、たとえ、精度が高くてもスピードが遅ければ、開発工程に組み込まれることが難しくなる。寸分違わぬものを、いかにハイスピードで生み出すか。この要求に応えるべく立ち上がったのが、商品開発チームでクレイモデル加工機を担当していたA.S.だった。クレイモデル加工機とは、工業用粘土を素材とした立体模型で実物大の自動車を設計し、デザイン検討をするためのモデル加工機であり、自動車のデザイン開発に欠かせない存在である。当時、世界最速のスピード、40m/min(メートル毎分)でクレイモデルを製造できる競合他社の加工装置があったが、A.S.はこれを大幅に超える60m/minを目標値として設定。「精度や速度、ユーザビリティはプロジェクトを成功させるためにマストですし、ユーザー視点からのものでしたが、当時の世界最速を遥かに凌ぐ60m/minというは自分たちで課した目標でした。TTSはここまでできるんだ、と世界に発信したい。どうせなら、高い目標を追いかけた方がワクワクしますからね。」A.S.は従来、モーターとギアで構成していた動力をリニアモーターに置き換え、高速化を追求。そして2024年11月に完成した試作機で公言通り、60m/minを記録し、世界最速を塗り替えた。

いかに優れたソリューションであっても、それが伝わらなければ意味がない。CPS構想を具現化するために奔走する開発チームとは別の場所で、もう一つの重要な戦いがあった。それはTTSが新たに提供しようとする価値を、社内外に「正しく、深く、魅力的に伝える」というマーケティングの挑戦である。その中心にいたのがN.K.。マーケティングの責任者として、彼がまず直面したのは、そもそもCPSという概念を自分自身が十分に理解していないという事実だった。「正直、最初は全くわかっていませんでした。」とN.K.は語る。フィジカルデータの取得、CAEによる解析、プロセスチェンジという専門用語の数々。どれも従来の装置販売を中心としたビジネスとは異なる文脈で語られるものであり、咀嚼するのに時間を要した。だが、自分が理解できていなければ、お客様に伝えられるはずもない。N.K.はDXチームのS.K.に繰り返し質問を投げかけ、会議の録音を何度も聴き直し、自身の中で「知る」から「分かる」、そして「語れる」レベルへと知識を引き上げていった。N.K.の役割は単なる“広報”ではない。CPSという新たな価値を、営業部門や顧客にとって「腹落ち」させる翻訳者であり、共感の橋渡し役でもある。自ら社内向けの勉強会を企画し、営業担当者とともに理解を深めながら、新商品の提案資料を構築。時には展示会を“学びの場”として活用し、顧客との対話を通じて理解の精度を上げていった。「やはり営業は、お客様の反応があると目の色が変わります。だからこそ、反応を引き出せるような“語り方”を整える必要がありました。」2024年末、30周年を迎えたプライベートショーでは、N.K.が磨き上げたプレゼンテーションが功を奏した。単なるスペック紹介に終始せず、自動車業界全体の課題にまで視野を広げた構成に、参加した役職者層の心が動いた。「製造業の未来を共に変えたい。」そんなビジョンへの共感が、イベント後のアンケート結果にも如実に表れた。

このCPS構想プロジェクトは、まだスタートラインにすぎない。S.K.は語る。「この構想を発展させていくことで、将来、劇的にモノづくりの工程を変えることができる。AIを駆使し、予測を早め、精度を高めることで、AIがデータを計測し、判断し、最適化する。そして人間が確認する。そんな世界がやってきます。“測る”価値からスタートし、プロセス全体を“導く”ような変革をつくっていく。」もちろん、実現には時間がかかる。しかし確実に、TTSはその未来に向かって歩みを進めている。CPS構想が社内に浸透し、顧客との対話も大きく変わってきた。「今、従来の装置のリプレイスのご相談であっても、CPSに関連する提案が求められるようになってきました。」とN.K.は言う。TTSは“測定機メーカー”としての看板だけではなく、“面白いことを仕掛ける会社”として、顧客からの期待を高まっていると言える。

A.S.は語る。「設計から製造、評価までのプロセスが、よりスムーズに、そして正確につながっていく未来をつくりたい。クレイモデルをはじめとした加工技術も、その未来の一部です。」TTSの世界最速のクレイモデル加工機は、単なるスペックの追求ではなく、“設計者の創造性を加速させるツール”としての価値を発揮している。TTSが描くのは、単なる製造支援ではなく、モノづくりの構造そのものを変える未来。サイバーとフィジカルの融合、AIによる判断の自動化、そして人とデータが共に意思決定する世界。そのために、TTSは「Digital System Integrator」として、製品の枠を超えた価値を提供していく。プロセスを変えるということは、産業の仕組みを変えること。そして、その仕組みの変革は、社会全体にも新しい可能性をもたらすはずだ。“測る”から、“導く”へ。その挑戦の旗は、いまも高く掲げられている。