金属の生産に不可欠な耐火れんがの設計・製造・販売など、鉄鋼業界向けに様々なビジネスを展開する東京貿易マテリアル(TML)。そんな同社がまた一つ、新たなビジネスを立ち上げようとしていた。これはセグメントの壁を超えて生まれたデジタルソリューションの物語である。

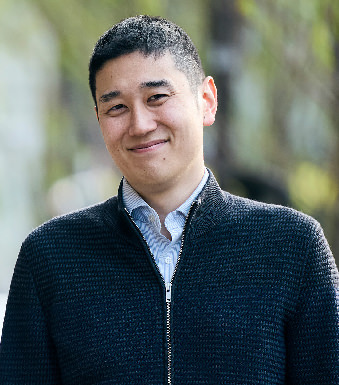
M.K.
営業本部 デジタル事業推進室チーフマネージャー
2010年入社 / 法学部・国際政治学科 卒
入社以来、耐火れんがの提案営業を行う。耐火物残厚測定システムビジネスの考案者であり、その流れでデジタル事業推進室に配属。チーフマネージャーを務める。

T.K.
営業本部 東日本営業部 千葉営業所 所長
2013年入社 / 経営学部 経営学科 卒
鉄鋼製品の輸出に3年間従事。その後、耐火れんがの提案営業を行い、現在は千葉営業所の所長としてマネジメントを手がける。

「なかなか簡単には売れないなあ…。」そう呟いたのは、TMLで金属メーカーに対して耐火れんがの提案営業を手がけてきたM.K.。2010年に入社して以来、千葉、東京、神奈川、岡山と各地域のクライアントを担当してきたM.K.だが、耐火れんがを提案するある種の難しさを感じていた。それは、耐火れんがという製品の品質が定量的に計測しづらいということ。耐火れんがは鉄をはじめとする金属の溶鉱炉で使用されるが、熱によって1回の使用で溶損(ようそん)して交換が必要になることもあれば、1年以上保つこともある。そんな製品だからこそ、品質の良し悪しが分かりにくく、中国工場から耐火れんがを供給しているTMLは「海外製だから品質が悪いのでは?」というイメージをもつクライアントもあった。また、品質の差が見えないからこそ、より良い製品に切り替えようという動きが起こりにくい状況もあったのだ。「販売につなげるために、何か新しい手立てはないか?」壁にぶつかったら、それをクリアするための作戦を練り上げる。トライアンドエラーの末に新しいものが生まれるという信念をM.K.は持ち合わせていた。M.K.がたどり着いた作戦は、耐火物の残厚を測定し、溶損量を計算するシステムを提案に組み込むこと。耐火物残厚測定システムで耐火れんがの寿命をデジタルに計測できれば現場の効率も上がり、耐火れんがの品質も定量的にクライアントに理解いただける。鉄鋼業界で耐火物残厚測定システムを保有するメーカーもあるが導入に1億円以上の費用がかかるシステムのため、限られた大手メーカーのみが利用しているという現状があった。

「もっと安価にシステムを提供できれば、商機はある。」M.K.が目をつけたのは、同じ東京貿易グループの東京貿易テクノシステム(TTS)。スマートマニュファクチャリングセグメントに所属する同社は、自動車メーカー向けに精巧な3次元測定装置を開発・販売していた。それを用いて耐火物を測定できないかと考えたのだ。最初に引き合いがあったのは、北陸のとある合金鉄メーカー。耐火物れんがが知らぬ間に溶損していては事故につながり、人命にも関わるため、システム導入を検討していた。M.K.はTTSと協議を重ね、要望に適うソリューションを組み上げていったが、簡単にはいかなかった。通常TTSが扱う自動車と比較して溶鉱炉は非常に巨大であり、測定しようとすると処理が重すぎてPCがフリーズしてしまう。また、ミクロン単位でモノゴトを考える自動車業界と、大きなスケールでモノづくりをしている鉄鋼業界では測定装置の設置にあたっても精密度が違う。様々な問題を解消するために、TTSのエンジニアを連れて何度もM.K.は北陸へ足を運んだ。そして2017年末、ついに初受注が決定。M.K.はこのビジネスを全国に広めるためにチラシを作成し、社内に発信した。

しかし、社内では「本当に売れるのか?」「違うことにリソースを使ったほうがいいのでは?」という意見が出るなど、反応はそこまで芳しいものではなかった。そんな中でこのチラシに食いついたのが、T.K.だった。2016年に耐火れんがの提案営業を行う資材部に異動してきたT.K.は、強い営業マインドを持っており、数字をつくることに意欲的だったが、新規提案が難航しているクライアントを担当しており、新たなアプローチ方法を探していたのだ。「M.K.さん、やりましょう!」T.K.はM.K.とともに京浜地区のステンレスメーカーを訪問。当初は耐火れんがやシステムの販売ではなく、耐火れんがの計測を無償で行うという方向性で提案し、話をまとめた。このケースは北陸の溶鉱炉の耐火れんがの測定と違い、溶解した合金鉄を輸送する鍋に使用される耐火れんがの測定であったことから、3次元で測定する際に工夫が必要だった。鍋を横倒しにして測定するなど、測定方法の調整に2年を要したが、最終的にはシステムの有用性が認められ、受注に成功。T.K.の熱意とM.K.のアイデアが噛み合ったこの成功によって、社内の空気が変わっていった。このソリューションを新しいビジネスの柱にするために、デジタル事業推進室が発足。M.K.がチーフマネージャーとして就任した。

耐火物残厚測定システムの提案エピソードとして、二人にとって思い入れ深いクライアントが、四国の金属メーカーだ。社内稟議を通すのが難しいクライアントであり、詳細な説明用資料が求められた。このシステムをなぜ導入する必要があるのか、どんな価値があるのか、TMLの責任の範囲、役割分担、スケジュールなどを明文化しなければいけない。さらにこれまでシステムの購入、無償の測定サービスは提案してきたが、今回のケースは、期間を決めてレンタルしたいというもの。契約形態も初めてだった。T.K.は様々な書籍や社内事例を調べて、資料を制作。クライアントからたくさんの指摘をもらいながら、ドキュメントをカタチにしていった。資料制作や提案は難航を極めたが、T.K.は持ち前の情熱と誠実さで向き合い続け、乗り超えていった。「最後に人を動かすのは情熱なんじゃないかなと思っています。そして、お客様が赤ペン先生のように丁寧にやってくださった。本当にありがたかったです。」そうT.K.は語る。この案件で制作したドキュメントはその後、システム販売時の提案資料のベースとなり、さらにビジネスが加速していくことになる。

「非常に有用なシステムであり、事故防止だけでなく、溶鉱におけるコスト効率を高めることにも寄与するものだ。」現在、全国数十社のメーカーにシステム導入が決まり、高評価の声が続々と届いている。これまで、大手の鉄鋼メーカーのみしか導入できなかったソリューションを多くのメーカーが利用できるようになった。「日本の鉄鋼業界のプレゼンスを上げることができたのではないか。」日本が海外に負けない競争力を身につける、その下支えがしたいとM.K.は言う。「先日、イタリア・ミラノで同システムの発表会に参加してきました。クライアントも海外に打って出ていく中で、私たちも共に進出したい。そのパートナーでありたいと思っています。」鉄鋼業界向けビジネスの多いTMLだが、今回はセグメントを超えてTTSと連携。業界を横断することで、新しいソリューションが生み出された。さらなるビジネスの立案、そして価値の創造。次に何を仕掛けるか、M.K.の目はきらきらと輝いている。


